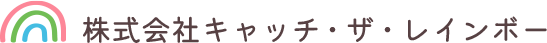「ごめんなさい」と「ありがとう」が言える子に育てたい ~その願いと葛藤のはざまで~
2025/04/22
放課後等デイサービスの現場で、私たち支援者が繰り返し子どもたちに伝えている言葉があります。
それは「ごめんなさい」と「ありがとう」。
この二つの言葉は、社会で人と関わって生きていくうえでとても大切な言葉です。自分の非を認め、相手の気持ちに寄り添う「ごめんなさい」。誰かの親切や優しさをしっかりと受け取り、感謝を表す「ありがとう」。
けれど、この言葉を心から口にすることは、実は大人でも難しいことがあります。ましてや、発達に特性のある子どもたちにとって、それがどれほど高いハードルかは、日々の療育のなかで何度も思い知らされます。
「言えている」けれど、心からじゃない?
子ども同士のトラブルは日常茶飯事です。おもちゃの取り合い、言い争い、順番のことでの小さなけんか。そんなとき、私たちはできるだけ早く介入し、状況を整理しながら、「どうしてこうなったのか」「相手はどう感じたか」を一緒に振り返ります。
そして、「ちゃんと『ごめんなさい』しようね」「『ありがとう』は?」と声をかける。
すると、多くの子どもは、うつむきながら、あるいは口をとがらせながら、絞り出すように言葉を発します。
「ごめんなさい……」「ありがと……」
その場では“言えた”ことにホッとしながらも、私の心に引っかかるものがあります。
本当にこの子は心から謝っているのだろうか?感謝しているのだろうか?
もしかしたら、私たち大人の指示に従って、形だけの言葉を発しているだけなのではないか……。
「言わせる」ことの難しさ
言葉の発達がゆっくりな子、相手の気持ちを読み取るのが難しい子、こだわりが強くて自分の非を認めたくない子――。
それぞれの子に背景があり、「ごめんなさい」や「ありがとう」という言葉がスムーズに出てこないのは当然のことです。
それでも、私たちは社会性の一環として、あるいは集団生活のルールとして、これらの言葉を“使える”ようにと指導していきます。
しかし、療育の現場で指導者として感じるジレンマは、「言わせる」ことで子どもが本当に理解できているのか、ということです。
「言わせる」ことは簡単です。でも、「言いたくなる気持ち」を育てることは、とても難しい。
心の中で感じていない「謝罪」や「感謝」の言葉は、子どもにとって単なる呪文に過ぎません。それでは意味がないし、子ども自身の成長にもつながりません。
子どもたちが言葉を「選ぶ」瞬間
だいぶ前ですが、小学4年生のAくんが、ブロック遊びの最中にBさんの作品を壊してしまいました。
Bさんは泣きながら「なんでそんなことするの!」と怒ります。私はそっとAくんのそばに行きました。
「どうして壊しちゃったのかな?」 「……邪魔だったから」 「Bさん、悲しそうだったね。あのブロック、ずっと作ってたの、知ってた?」 「……うん」
しばらく沈黙のあと、Aくんがぽつりとつぶやきました。
「ごめん」
私はその瞬間、心がじんと熱くなりました。
誰に促されたわけでもなく、Aくんが自分の気持ちで「ごめん」と言った。その言葉には、確かに気持ちがこもっていました。
私たちが目指したいのは、まさにこういう姿です。
指示されなくても、自分の気持ちに気づき、自分で言葉を選んで、相手に伝える。
それができるようになるまでには、時間がかかるかもしれません。でも、それでいいのです。焦らず、ひとつひとつの出来事に丁寧に向き合いながら、その“瞬間”を育てていきたいのです。
支援者としての“迷い”と“希望”
正直に言えば、支援者として迷うこともたくさんあります。
「この対応でよかったのか?」 「もっと別の言い方をすればよかったのでは?」 「今日はあの子にとってしんどすぎたかもしれない」
そうやって帰り道に思い悩み、夜中にふと目が覚めてしまうこともあります。
でも、私たち支援者の役割は、“正解”を提供することではなく、“寄り添い”を提供することだと考えています。
子どもたちの小さな変化に気づき、それを言葉にして伝えること。失敗を叱るのではなく、「次はこうしてみようか」と前向きな提案をすること。
何よりも、「ごめんね」「ありがとう」が言える空気を、場としてつくること。
私たちがその雰囲気を大切にしていれば、きっと子どもたちにも伝わるはずです。
最後に:言葉の奥にある「心」を信じて
----------------------------------------------------------------------
児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町381-8
電話番号:0284-64-9483
生活介護 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町388-3
電話番号:0284-64-8135
足利市の児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
足利市周辺の放課後等デイサービス
足利市にて小児リハビリのケア
足利市で重症心身障がい児の対応
----------------------------------------------------------------------