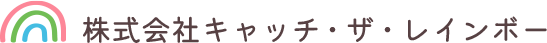〜七夕飾りを玄関前にて〜
2025/07/01
今年も七夕の季節がやってきました。施設の玄関先には、立派な笹にたくさんの短冊と折り紙の飾りをつけて、子どもたちの願いを飾りました。紙の星やハート、色とりどりの折り鶴、チェーン飾りに囲まれながら、揺れる短冊にはそれぞれの想いが記されています。
「アイスクリームがいっぱい食べられますように」
「ママともっと遊べますように」
「世界が平和になりますように」
ひらがなで一生懸命書かれたものもあれば、職員と一緒に話し合って書いたと思われる少し難しい内容の短冊もありました。
近視眼的になりがちな私たち
日々、子どもたちと関わっていると、つい目の前のことばかりに追われてしまいます。今日の活動は無事に終わるか、体調の変化はないか、スケジュール通りに送迎できるか、保護者への連絡は漏れていないか……。
どれも大切な仕事ではありますが、ふと気がつけば「こなすこと」が目的になってしまっている瞬間もあるかもしれません。
しかし、そんな時に子どもたちが書いた短冊を読むと、まるで「ちょっと立ち止まってごらん」と語りかけられているような気がします。
「せかいへいわ」
「びょうきがなおりますように」
そんな願いを前にすると、自分たちが見えていなかった「もっと広い世界」を思い出させてくれるのです。
子どもたちのまなざし
私たちは「子どもはまだ世界のことを知らない」と思いがちですが、実際にはとても鋭い感性を持っています。
「遠くの国で戦争が起きてるんだって」
「地震のニュースを見たよ」
「パンダが中国に帰っちゃったんだって」
テレビや絵本、保護者や職員の話を通じて、子どもたちは自分の外にある世界にしっかりと目を向けています。そして、自分がどう関わっていけるかを考えようとしている姿があります。
「○○くんが元気になりますように」
「おともだちができますように」
これはもう「祈り」と言ってもいいのかもしれません。他人の幸せを願う力、それが自然に湧き上がってくる子どもたちの感性は、私たち大人が学ぶべきものではないでしょうか。
「願い」を書くということ
短冊を書くという行為は、自分の内面を外に出す作業でもあります。普段はうまく言葉にできなかった気持ちが、「〜ように」という形を借りて初めて姿を現すこともあるのです。
ある子は「もっとあそべますように」と書いてくれました。これには深い意味があるかもしれません。「今はあまり遊べていない」と感じているのかもしれませんし、「あそぶ時間がもっとほしい」という心の声かもしれません。
大人が丁寧にその声に耳を傾ければ、支援のヒントが見えてくることもあります。七夕という機会は、単なるイベントを超えて、子どもたち一人ひとりの心の扉を少し開いてくれる時間なのです。
私たちにできること
七夕の笹は、季節が過ぎれば片付けられてしまいますが、そこに書かれた願いは、私たちの心に残しておきたいと思います。
私たちにできることは、願いを叶えてあげることだけではありません。願いを「受け止める」こと、そして「見守る」こと。ときには一緒に願ってあげること。
それが子どもたちの心に「誰かが私のことを気にかけてくれている」という安心をもたらし、自信と意欲につながっていくのではないでしょうか。
おわりに
玄関に風に揺れる笹の葉と色とりどりの短冊。子どもたちの願いは、決して小さなものではありません。むしろ、大人が忘れかけていた大切な視点を思い出させてくれる存在です。
私たち職員も、七夕のこの季節に「原点」を振り返りながら、また明日からの支援に心を込めて取り組んでいきたいと思います。
----------------------------------------------------------------------
児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町381-8
電話番号:0284-64-9483
生活介護 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町388-3
電話番号:0284-64-8135
足利市の児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
足利市周辺の放課後等デイサービス
足利市にて小児リハビリのケア
足利市で重症心身障がい児の対応
----------------------------------------------------------------------