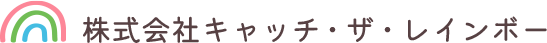重症心身障害児・医療的ケア児の夏休み後半の過ごし方 ― 生活リズムを整えて新学期に備える ―
2025/08/20
はじめに
栃木県足利市をはじめ、関東地方は今年も連日猛暑日が続いています。重症心身障害児や医療的ケア児にとって、この強い暑さは大きな負担となりやすく、体力の消耗や自律神経の乱れ、生活リズムの崩れにつながりやすい時期です。
特に夏休み後半は、学校再開に向けて「生活リズムを整え、体調を安定させる」ことが大切になります。今回は、猛暑の中での体調管理の工夫と、自律神経系を整えるための刺激方法、さらに新学期へスムーズに移行するための生活リズムづくりについて考えてみましょう。
1. 夏の疲労と生活リズムの乱れ
1-1 夏の疲れが出やすい理由
猛暑が続くと、体温調節に大きなエネルギーを消費します。さらに冷房の効いた室内と屋外の温度差が大きいため、自律神経が常に刺激されて疲労が溜まりやすくなります。
医療的ケア児の場合、吸入や経管栄養などの日課に加え、体調の変化に敏感に対応する必要があるため、家族の負担も大きくなります。
1-2 生活リズムが崩れる要因
学校がないため就寝・起床時間が遅れやすい
外出が減り、昼間の活動量が低下する
水分不足や食欲低下でエネルギー不足になりやすい
医療的ケアのタイミングがずれ、日課のリズムが乱れる
こうした要因が重なり、夏休み後半になると「疲労感が抜けない」「夜眠れない」「朝起きられない」というリズムの乱れにつながるのです。
2. 学校に向けて生活リズムを整えるポイント
2-1 就寝・起床時間を少しずつ戻す
新学期が始まってから急に「早寝・早起き」に切り替えるのは難しいものです。
1日15~30分ずつ、起床・就寝時間を学校モードに近づける
朝はカーテンを開けて自然光を浴びる
夜は照明を落とし、テレビやタブレットの使用を控える
光の刺激は体内時計を整える重要な要素です。自然光や室内照明をうまく活用し、睡眠リズムをサポートしましょう。
2-2 食事と水分補給の安定
栄養と水分補給は生活リズムの基本です。
経管栄養の時間を学校生活に合わせて調整
水分補給はこまめに。経口摂取が難しい場合は、冷却タオルなどで体温を下げて熱中症予防
食欲が落ちる時期は、少量でも消化のよいものを取り入れる
食事の時間を安定させることで、体内時計もリズムを取り戻しやすくなります。
2-3 昼間の活動量を増やす
暑さで外出が難しい場合でも、室内でできる活動を工夫することが大切です。
手足のストレッチ
音楽に合わせてリズム運動やタッチング
光や水、風を使った感覚遊び
昼間に体を刺激することで、夜の睡眠が深まりやすくなります。
3. 自律神経を整える工夫
3-1 体温調整で自律神経をサポート
足浴や手浴で「温かさ」と「涼しさ」を感じる体験
ミストスプレーや冷却タオルを用いた心地よい冷感刺激
入浴時にぬるめのお湯にゆっくり浸かることでリラックス
温度の変化を感じることは、自律神経への自然な刺激となります。
3-2 呼吸を意識した関わり
人工呼吸器や吸引など医療的ケアがある場合でも、「呼吸のリズムを感じる」ことは大切です。
ゆったりした音楽に合わせて一緒に呼吸を意識する
抱っこやタッチングで呼吸のテンポを整える
吸入後の安定した呼吸を確認しながらリラックス
これらは副交感神経を優位にし、安心感につながります。
3-3 感覚刺激を取り入れる
光(自然光、やわらかいランプの光)
音(小さな鈴、オルゴール)
風(扇風機、うちわ)
強すぎない刺激をバランスよく取り入れることで、自律神経のバランス調整を助けます。
4. 猛暑時期の体調管理の工夫
4-1 クーラーと湿度管理
猛暑の足利市では冷房が必須ですが、冷えすぎや乾燥にも注意が必要です。
室温は26~28℃を目安に
加湿器や濡れタオルで湿度を保つ
定期的に換気を行う
4-2 水分・塩分補給
経管栄養児の場合は、水分量を医師や看護師と相談し調整
発汗が多い日は経口補水液を取り入れる
家族も一緒に「水分をとる習慣」を持つことで自然にケアできる
4-3 家族の疲労にも目を向ける
夏休み後半は保護者も疲れが溜まりやすい時期です。
ショートステイやレスパイトサービスの活用
家族内での役割分担を見直す
介護者の休息時間を意識的に確保する
5. 新学期に向けた準備
5-1 学校生活へのシミュレーション
登校時間に合わせた起床・準備の練習
登下校に必要な物品(吸引器・酸素ボンベなど)の点検
学校側と体調面の情報共有を行う
5-2 精神的な安心感づくり
夏休みの思い出を写真や作品で振り返る
新学期に楽しみにしていることを一緒に話す
短時間でも外出して「季節が移り変わっていること」を体感する
おわりに
夏休み後半は、子どもたちにとって「楽しい時間の名残」と「新学期への準備」が重なる時期です。特に重症心身障害児・医療的ケア児にとっては、生活リズムの安定と体調の調整がとても大切になります。
猛暑で体力を消耗しやすい足利市の気候を踏まえながら、家庭や施設で無理なく取り入れられる工夫を重ねていくことで、安心して新学期を迎えることができるでしょう。
「小さな一歩を毎日積み重ねる」ことが、子どもたちの健やかな笑顔と、家族の安心につながります。
----------------------------------------------------------------------
児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町381-8
電話番号:0284-64-9483
生活介護 虹をつかもう
栃木県足利市八椚町388-3
電話番号:0284-64-8135
足利市の児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう
足利市周辺の放課後等デイサービス
足利市にて小児リハビリのケア
足利市で重症心身障がい児の対応
----------------------------------------------------------------------